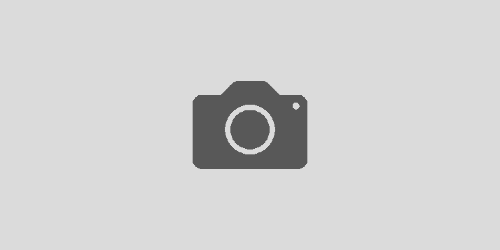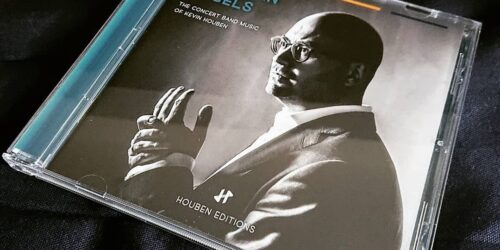IBK2020(国際吹奏楽コングレス)に参加する作編曲家をまとめてみた
17.José Schyns/ジョセ・シンス
1959年、ベルギー・モレスネット出身。リエージュの音楽院で学んだ後、ベルギー・ギィデ交響吹奏楽団でソロトロンボーン奏者を務めるほか、王立音楽院でトロンボーンの授業を受け持つ。管弦楽作品の吹奏楽版アレンジャーとしても活躍している。
講演内容)トランスクリプション(管弦楽作品等の吹奏楽向け編曲)におけるインストゥルメンテーション、オーケストレーション
自分がどうしてアレンジをするようになったのか、といった自己紹介から始まり、自身がアレンジ作業の上で使っているテクニックについても紹介してくれる。
18.Gilbert Tinner/ジルベール・ティンナー
1965年、スイス・ザンクトガレン出身。幼いころからトロンボーンとピアノのレッスンを受け、ジャズスクールでトロンボーン・ピアノ・作曲・編曲を学ぶ。数多くの吹奏楽向けのジャズ/ポップス曲のアレンジに加え、吹奏楽やブラスバンドのためのシャッフルロックスタイルを含む作品を作曲している。
講演内容1)ポップミュージックの吹奏楽向けアレンジ
ジャズ、ポップス、ロック音楽を吹奏楽向けに編曲することの難しさ、アレンジの基本、アレンジする作品の選択について。
講演内容2)ウインドバンドによるポップス、ジャズ作品の演奏について
フレージング、音調バランス、アーティキュレーションの取り扱いなど、ポップス/ジャズを演奏するにあたっての注意点を、実際に楽器を演奏しながら学べるワークショップ。
19.Thomas Trachsel/トーマス・トラクセル
1972年、スイス・オルテン出身。8歳でツィター(スイス周辺で使われる弦楽器)のレッスンを受け、次いで音楽学校でトランペット・ピアノのレッスンを受け、個人的に音楽理論を、音楽アカデミーで吹奏楽指揮を学ぶ。
現在は主に吹奏楽団、ブラスバンド、交響楽団の指揮者として活動。作曲家としては4つの交響曲を含む大規模な作品で知られる。
講演内容)生きるための作曲? 作曲する人生!~作品紹介~
スイスの音楽祭やスイスナショナルユースブラスバンドの委嘱を中心に、100以上の作品を作曲してきたトラクセル。彼の作品の多様性、個性、また作品のバックに存在する人物についても語られる。
20.Jan Van der Roost/ヤン・ヴァンデルロースト
1956年、ベルギー・デュフェル出身。幼いころからバンドでトロンボーンの演奏を経験し、レメンス音楽院でトロンボーン・音楽史・音楽教育を、ヘントとアントワープの王立音楽院でフーガ・作曲・合唱指揮を学ぶ。多くの吹奏楽作品のほか、管弦楽、合唱、室内楽のための作品も精力的に手掛ける。
日本でも「スパルタクス」「アルセナール」「プスタ」「モンタニャールの詩」など、多くの作品が広く演奏されている。
ヴァンデルローストが「あとの50%」と呼ぶ種の作品の一つ、アルトサクソフォン協奏曲
講演内容1)50%は吹奏楽の作曲家、残り50%は…?
吹奏楽の分野で広く知られているヴァンデルローストだが、それ以外にも合唱、管弦楽、室内楽など、実は多種多様なスタイルの作品を書いており、2018年には声楽作品のみの作品集アルバムもリリースしている。自身の吹奏楽作品はもちろん、それ以外のスタイルの最新作のいくつかを紹介する。
講演内容2)「インストゥルメンテーション」と「オーケストレーション」の違いとは
講演者は「インストゥルメンテーション」には「楽器についての正しい理解(機能性)」が必要であり、「オーケストレーション」にはさらに芸術的な意味が加わる、と述べる。ブラスバンド作品が吹奏楽編成用にアレンジされるなど、異なる編成に編曲される場合、それらは何時、純粋に「機能的(商用的)」であり、何時「芸術的」と言えるのだろうか。