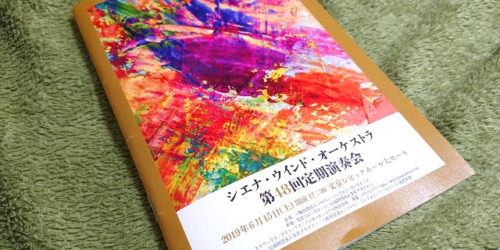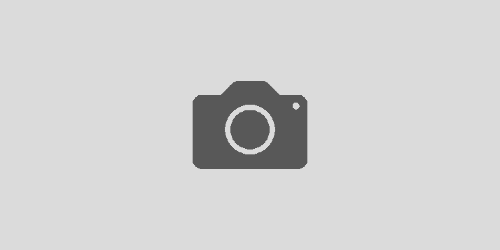IBK2020(国際吹奏楽コングレス)に参加する作編曲家をまとめてみた
1.Stephan Adam/シュテファン・アダム
1954年、ドイツ・ヘッセン州出身。教会音楽を学んだ後、合唱指揮、作曲の研究に励む。彼の音楽作品は、古典的なスタイル、また鋭く響く不協和音が特徴。作品は室内楽、管弦楽、合唱、吹奏楽、オルガンのための作品まで多岐にわたる。
2014年にオラトリオ「クリスマスの停戦、1914」を作曲。第1次世界大戦の最中、1914年のクリスマス、一時的に非公式に停戦した出来事を題材としている。
講演内容) Composer’s Portrait ~作品紹介~
吹奏楽バンドのための初級作品”Fanal 1″“Fanal 2”、中級作品“Toccatina”、上級作品”Suite barlesque”(リンク先で試聴できます)
2.Bert Appermont/ベルト・アッペルモント
1973年、ベルギー・ビルゼン出身。国内の音楽院で音楽教育と指揮を学んだ後、イギリスへ留学して映画・テレビのための音楽デザインを学ぶ。ミュージカルや交響曲を含む多くの吹奏楽作品に加え、管弦楽作品や合唱作品を作曲。テレビ、映画にも音楽を提供している。自身で作曲のみならず作詞も手掛けた、青少年のための合唱曲集”Liedjekeuk”シリーズも興味深い。(ex. De tovennaar)
日本でもトロンボーン協奏曲「カラーズ」、「ノアの箱舟」、「ブリュッセルズ・レクイエム」で知られる、大人気作曲家。
講演内容) 作曲への異なるアプローチ-商業的側面と作曲の技術との間の緊張-
自身の芸術性に従い、音楽性の高い作曲を目指しつつ、青少年・アマチュアバンドにも作品を演奏してもらうためにはどうすればよいか…日本の吹奏楽界隈でも時々議論が起こるトピックについてアッペルモントが語る。
3.Franco Cesarini/フランコ・チェザリーニ
1961年、スイス・ベリンツォーナ出身のイタリア系スイス人。音楽院でフルートとピアノを学び、スイス独奏コンクールでフルート奏者として第1位に輝いた経験も持つ。その後音楽理論と指揮法も学び、現在では世界中で人気の作曲家に。日本でも「アルプスの詩」「青い水平線」、交響曲第1番「アークエンジェルズ」などで知られている。
2020年4月には来日し、オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラと共演予定。最新の交響曲第2番「江戸の情景」を自作自演する。
講演内容1) 指揮のマスタークラス
フィリップ・スパーク「ドラゴンの年」、フランコ・チェザリーニ「ブルガリアン・ダンスパート2」、ジェームズ・バーンス「交響曲第2番」を用いて、指揮法の座学と実践のマスタークラスを行う。
講演内容2) 管弦楽作品のトランスクリプション(吹奏楽編成への編曲)について
作曲と編曲の境界はどこ?バンドのための編曲がどれだけ元のキャラクターを保持できるか、そのためのアプローチは?またそれを確認する方法とは?作曲だけでなく、管弦楽作品のアレンジでも安定した人気を誇るチェザリーニが語る。
4.Jacob de Haan/ヤコブ・デハーン
1959年、オランダ・ヘーレンフェーン出身。学校音楽とオルガンを専攻し、またアレンジ法も学ぶ。多数の吹奏楽曲に加え、20~40分に及ぶオラトリオも複数手掛ける。ちょっぴり懐かしの歌謡曲的な雰囲気のある、ダイナミックでポップな作風が特徴。
同じ姓で同じく作曲家のヤン・デハーンは実の兄。
この編成の小ささでこの迫力、なんやねん
講演内容) Composer’s Portrait ~作品紹介~
ヤコブ・デハーンの代表作「オレゴン」が出版から30周年、「コンチェルト・ダモーレ」が25周年。その他「ロス・ロイ」「ラ・ストーリア」「ダコタ」「バージニア」など、数多くの人気作品を生み出した彼の作曲の成功の秘訣とは。長年の音楽活動の中で、いったい彼の音楽はどのように発展してきたのだろうか。