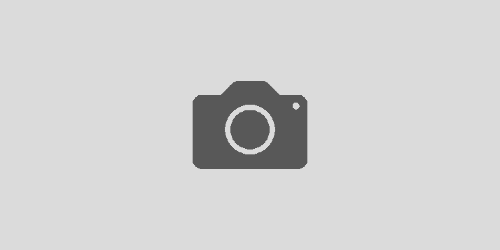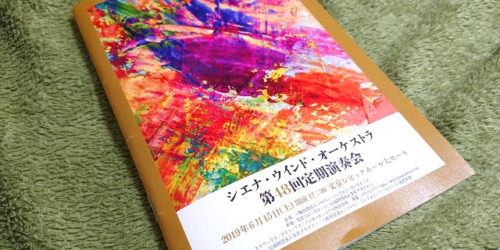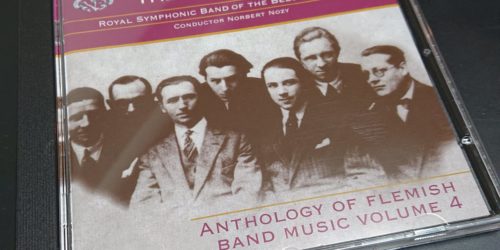IBK2020(国際吹奏楽コングレス)に参加する作編曲家をまとめてみた
5.Thomas Doss/トーマス・ドス
1959年、オーストリア・リンツ出身。管弦楽団のトロンボーン奏者の両親のもと、幼少期からテナーホーン、トロンボーンのレッスンを受ける。音楽院でトロンボーン、作曲、指揮、ピアノを学び、ジョン・ウィリアムスのもとで研修員として働いた経験も持つ。
作品の多くはシネマティックで、独特の広がりのあるサウンドが特徴的。日本では「シダス」「セントフローリアン・コラール」などが知られている。
ドスさんは個人的にブラスバンド作品が大好きである
講演内容)交響曲第3番の発表
1月5日に初演されたばかりの交響曲第3番「Symphony of Freedom(自由の交響曲)」を、IBKでも発表。フリードリヒスハーフェン・シティ・オーケストラ(Stadtorchester Friedrichshafen)の演奏、作曲者自身の客演指揮で。
6.Miguel Etchegoncelay/ミゲル・エチェゴンセレー
1970年、アルゼンチン・コルドバ出身。アルゼンチン・イタリア・スイス・フランスでトランペット・指揮・作曲を学び、フランコ・チェザリーニやティモシー・レイニッシュにも師事。
管弦楽団や吹奏楽団の指揮者として活躍する傍ら、作編曲も精力的に行っている。
講演内容1)リーディングセッション「新しい吹奏楽作品を知る」
WASBE(世界吹奏楽協会)作曲コンテスト受賞作品や出版社ブースの展示作品の中で、グレード0.5~3.5の新作を取り上げ、簡単な解説と初見合奏を行う。
講演内容2)ラテンアメリカの吹奏楽作品
ヨーロッパでは(もちろん日本でも)あまり知られていない、ラテンアメリカの若い作曲家の吹奏楽作品を紹介する。
7.Mathias Gronert/マティアス・グロナート
1976年、ドイツ・ヴォルファッハ出身。9歳からトランペットを習い、チューバと音楽理論の7年間の訓練を受ける。ウインドバンドの指揮者としての教育を受け、吹奏楽専門のレコーディングスタジオのサウンドエンジニア、また作曲家・アレンジャーとしても活動している。
ポルカをよく作曲しているみたいです
講演内容)GEMA(ドイツの音楽著作権管理協会)について
偏見や噂、憶測を排除し、GEMAの重要性と音楽の文化遺産という意味における著作権の理解を進める。JASRACについて毎日のように議論・誹謗中傷が飛び交う日本の音楽シーンから見ても興味深い講義内容。
8.Hubert Hoche/フーベルト・ホッヘ
1966年、ドイツ出身。大工見習を経て、音楽大学で作曲と指揮を学び、大学院で作曲の研究を続ける。作風はかなり現代(前衛)的だが、難易度は幅広く、初級バンドでも現代音楽を演奏できる。吹奏楽・バレエ・ビジュアルアートのためのバレエ作品「MYSTIKA」を2017年に初演した。
講演内容1)グレード3.5~6の作品紹介
Melancholy Moment(憂鬱な瞬間)、HOPE、Back from the other side、バレエ作品”MYSTIKA”、Black-White-Blue
講演内容2)青少年バンドのための音楽祭「Festival UNerHÖRTes」のプレゼンテーション
UNerHÖRTes、ドイツ語で「前代未聞」と名付けられたこのイベントは、ドイツ・ハンメルブルクのバイエルン音楽アカデミーで、2012年以降、定期的に開催されている、初級・青少年バンドのための音楽祭。
参加したバンドは、この音楽祭のために委嘱された新曲のリハーサルを、作曲者自身の指揮で経験できる。
バンドの参加費は無料、北バイエルン音楽協会が旅費まで助成してくれるそうだ。羨ましい。
2017年開催時のレポート(ドイツ語)
講演内容3)NEW EARS – ウインドバンドプロジェクト
NEW EARSは、吹奏楽のコンテンポラリー作品に焦点を当てたプロジェクト。プロジェクトの中心的な立場にあるホッヘと、同じく中心人物である指揮者のマイケル・ガイガー(Michael Geiger)が、2019年の初コンサートの報告を兼ねてプレゼンテーションを行う。
NEW EARSのFacebookページ